別府念仏踊(べっぷねんぶつおどり)

指定年月日
昭和43年4月5日(県指定)
所在地
別府念仏踊保存会
概要
念仏踊は別名を腰輪楽ともいう。この踊りは毎年9月初頭に執行される厳島神社秋の例祭において堅田下組から1楽、江原組もしくは堅田上(芹田・湯の上)組から1楽との2楽が奉納される。弁天池の水の恵みに感謝し豊年を祈るものだといわれている。
踊りは鶏頭をかたどる板を中心に5種類の色和紙製の花で飾りたてた花笠をかぶり、胸に締太鼓を装着した「頭取」2名と「杖」少年2名、「大内輪」少年2名、「小内輪」少年2名、「鉦打」幼少年8名の役で構成されている。頭取は太鼓をリズムよく打ち鳴らしその動きは雄鶏の闘いを表している。鉦打は太鼓のリズムに和して鉦を打ち、大内輪・小内輪は頭取を鼓舞するかのように特製の大団扇を振りながら踊る。杖は向き合うと気合いを入れてリズムよく樫の棒を打ち付け合い踊りの開始を告げ、また踊りの終わりを締めくくる。この他に「年寄」「幟」2名、「鉄砲」2名の役がある。年寄は踊りを総括する重要な役で裃を着用する。幟は行列を先導する。鉄砲は踊りの前後に発砲する。
頭取と鉦打は竹の輪に紅白の短冊を付けた腰輪を着用する。「腰輪楽」の呼称はこれによる。また、念仏踊の名称は念仏宗に端を発した神仏習合の名残だと考えられる。この踊りの由来は「防長寺社由来」・「防長風土注進案」に記録されている。特に後者の記述は「嘉万村」の開闢伝説と併せて詳細である。
堅田下組上会講には「當屋控帳」が保存されている。これは、文化8年(1811)から昭和の末年までの記録で特に幕末期のこの踊りを支える会講組織と運営の実態がつまびらかであり、また神道興隆と神仏分離の影響さえもうかがえるのである。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 文化財保護課
〒759-2212
美祢市歴史民俗資料館内
美祢市大嶺町東分279-1
電話番号:0837-53-0189
ファックス:0837-52-1082
bunkazai@city.mine.lg.jp
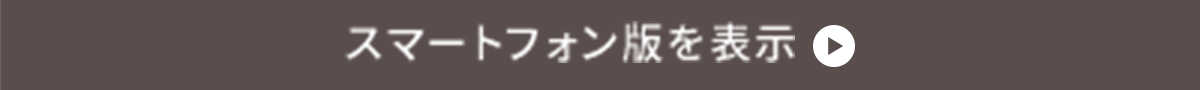












更新日:2020年10月01日